【海外騒然】 царская ванна!?巨大すぎる風呂に世界がマジ困惑
今回のYouTube動画は、History by Maeによる「The bathtub of Tsar Alexander」という歴史とアートに関するものです。動画では、ツァーリ・アレクサンドルの浴槽について解説されています。400万回以上再生されている人気の動画ですが、そんな動画に対する海外の反応はどうでしょうか?
驚きと興奮の声が多数!
ええい、奴ときたら、もう屍のようにプカプカ浮いて、スープの藻屑と消える運命じゃ!時折、脳裏をよぎるは「もし、このまま息継ぎをしなかったらどうなる?母なるロシアは滅びてしまうのか?全てはこのワシが顔を上げるかどうかにかかっているのだぞ!…いや、そもそも、そんな価値はあるのか?もう2分半も経っておる…」と、憂鬱極まりないロシア人よ!
プールのサイズ、マジ最高じゃん!!
え、ちょ、待って!その銀色のロケット、マジで何!?めっちゃ気になるんだけど!😍 サンキュー!一体何が入ってて、どんな意味があるんだ!?教えてくれよ、頼む!
ピーウィーの大冒険でわがままな坊っちゃんが使いそうなバスタブじゃねぇか!アハハ!
巨大な巨人族が使うスープボウルか、はたまた極楽ホットタブか!?こりゃあ一体どっちなんだい!?
マジか!これはパーティー用ジャグジーに違いない!しかも自作の泡だと!?😂💨 こりゃヤバすぎるぜ!!
マジかよ!それ、めっちゃ興味深いじゃねーか!!
「俺たちは浴槽で溺れたんだ。」「3人全員で?」「デッッッカイ浴槽さ。」 (誰かこれの意味を教えてくれぇぇぇ!頼む!)
一体どうやって水抜くんだ!?それにどうやって入るんだよ!? なんでこんなにデカいんだ!? 質問攻めじゃー!!😂
マジかよ!こんな風呂に一度でいいから浸かってみたいぜ!!!
さあ、プールヌードル体験の時間だ!(一部の人には脳ミソフル回転案件かもな!)
ユニークな発想に困惑?
マジかよ…一体ぜんたい…なんでやねん!!!
ちょ、マジか!?こんな深さの湯船でリラックスとかありえん!アーム浮き輪必須だろ、マジで!! FFS!!!
マジか!自分の風呂場で溺れる可能性とか、ありえねぇ!一体どうやって出入りするんだ!?オーマイガー!😮
マジかよ!溺れてたかもしれんじゃん!アブねー😮
マジかよ、これマジでずっと見ちゃうんだけど、何度見てもニセモノに見えんだよなぁ!?一体どうなってんだ、コレ!?
批判的な意見もちらほら
誰も俺たちができないなんて言ってないだろ!まさかエイリアンの技術だとでも言うのか?!ああ、金持ちだからできるんだな…クソッ!
敵を煮詰めて犬に食わせるぞ!ヒャッハー!
ああ、なるほどね、「バスタブ」か!ナチスがそれを欲しがったって?そりゃそうだ!だって、あいつらが秘教的なバスタブ技術にハマってたなんて、誰もが知ってることじゃないか!ハッハッハ!!
ナチども、世界の宝を盗もうとする姿がマジで笑えるわ!「選ばれし民族」だって?ハッ、世界の素晴らしいものは全部他人が作ったものじゃねーか!自分じゃクールなもん何も作れねーのかよ、あぁん!?
ツァーリ・アレクサンドルの巨大な浴槽に対する海外の反応は、その大きさと実用性への疑問、そして歴史的背景への興味が入り混じった、まさに「驚き」の一言に尽きるようでした。一見すると奇妙に思える巨大な浴槽に、畏敬の念を抱いたり、ユーモアを感じたり、陰謀論に結び付けたりと、様々な感情を抱く様子は、日本のユニークな文化や歴史に対する海外の多様な視点を反映していると言えるでしょう。この浴槽のように、日本には世界の人々を惹きつけ、時に困惑させる、他に類を見ない魅力がまだまだ眠っているのかもしれません。

動画の浴槽、大きすぎますよね!小さい頃、銭湯で溺れかけたのを思い出しました。イギリスのスパも好きですが、日本の温泉のほうが落ち着くのは、やっぱりDNAのせいでしょうか。
💡 豆知識
日本の浴槽の歴史は古く、飛鳥時代には仏教とともに湯浴みの習慣が伝わり、蒸し風呂のようなものが使われていたそうです。江戸時代になると銭湯が普及し、庶民も気軽に湯を楽しめるようになりました。昔は五右衛門風呂のようなものもありましたが、現在のような家庭用浴槽が一般的になったのは、戦後の高度経済成長期以降ですね。さて、近年、海外の方が日本の浴槽に注目しているのは、単なる入浴という行為以上の価値を見出しているからでしょう。まず、その深さに驚かれます。肩まで浸かれる深い浴槽は、全身をリラックスさせ、浮遊感を楽しむことができる特別な空間です。次に、追い焚き機能もポイント。いつでも好きな時に温かいお湯に入れるのは、海外では珍しい機能です。さらに、入浴剤やアロマなど、お湯の質や香りを自分好みにカスタマイズできる点も魅力。忙しい現代人が、心身をリフレッシュできる場所として日本の浴槽に注目し、「お風呂に入る」という行為そのものを、まるで瞑想のように捉えているのかもしれませんね。単に体を洗うだけでなく、一日の疲れを癒し、心を整える時間として、日本のバスタイムが再評価されているのでしょう。
英語
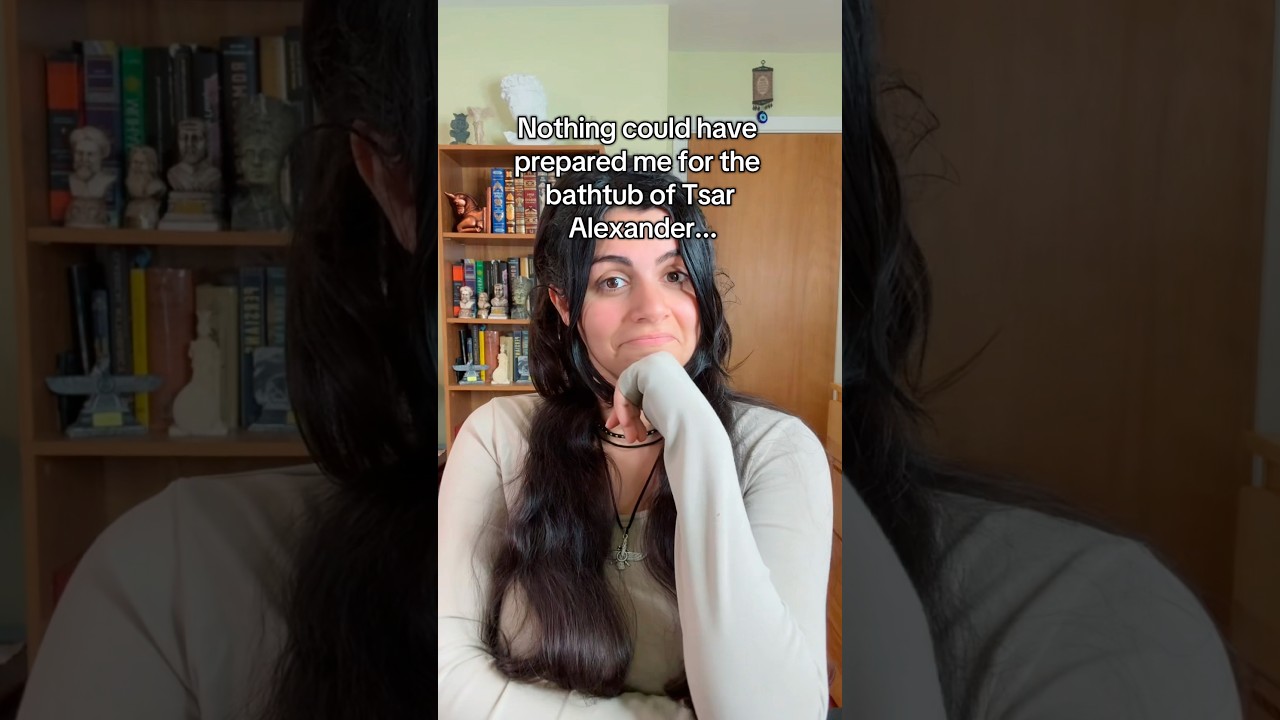



🕒 2025-11-07T11:16:53Z